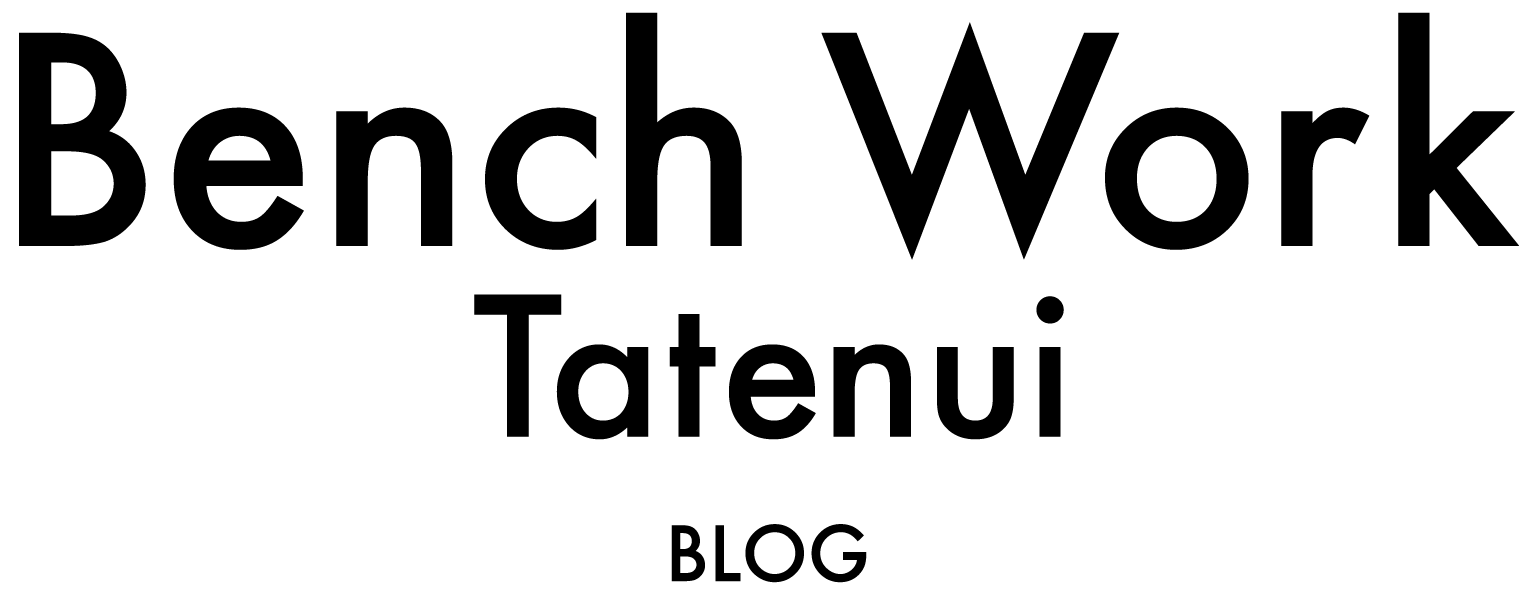スツールが 『疲れにくい』 理由
部屋に置く椅子を選ぶとき、多くの人が「長く座っても疲れにくい椅子」を探すと思います。
不思議なことに、背もたれのない木のスツールなのに、「思ったより疲れない」「むしろ心地いい」と感じてくださる方が少なくありません。
なぜなのでしょうか。一見矛盾するようにも思えますが
Bench Work Tatenuiの視点から、その理由をお話しします。
姿勢を“委ねすぎない”という心地よさ
ふかふかの椅子に深く沈み込むと、一見リラックスしているようでいて、実は腰や首に負担がかかることがあります。
「疲れにくさ」は、柔らかさよりも「無理のない姿勢」が保てるかどうかにあります。
スツールは、必要以上に身体を甘やかしません。
座面に腰を預けたとき、自然と骨盤が立ち、足裏がしっかり床を捉えます。
背もたれがない分、上半身の位置を自分でそっと整える感覚が生まれ、その“自律した姿勢”が長く座ったときの疲れにくさにつながります。
ほんの少しだけ意識を促す椅子。
それが、良いスツールの役割のような気がしています。
木の質感が生む「留まりすぎない快適さ」
スツールは「ずっと座り込むための椅子」ではなく、
作業の合間、身支度、読書、会話──短くも豊かな時間に寄り添う道具です。
Bench Work Tatenuiの採用している座面は、触れるとあたたかく、適度な硬さがあります。
この「硬すぎず、柔らかすぎない」感触は、身体にとって目安のようなもの。
必要な分だけ座り、用が済めばすっと立ち上がる。
その切り替えのしやすさが、結果として身体の負担を溜め込まないことにつながります。
長時間“縛りつけない心地よさ”もまた、疲れにくさの一つのかたちです。
余白を計算したかたちとプロポーション
Bench Work Tatenuiの木のスツールは、座面のサイズ、高さ、脚の位置、面の取り方まで、すべて「人の動き」とセットで考えています。
深く腰をかけても、浅くちょこんと座っても安定する座面。
足を少し開いて重心を落とせる脚の開き。
縁に手を添えたときの指先に心地よい感触。
それらは目立たない工夫ですが、
「なんとなく座りやすい」「姿勢が決まりやすい」という感覚として現れます。
数字や理論よりも、実際に座ったときの体の落ち着き方を指標に、一本一本かたちを整えています。
出雲の空気の中で育つ、木の呼吸
無垢の木は、出雲のしっとりとした空気の中で、ゆっくりと乾き、落ち着いていきます。
急激に乾かさず、木の内部のストレスを抑えることで、座面に触れたときの当たりがやわらかくなり、艶も深まります。
その木を使ったスツールは、時間とともに手触りが馴染み、
座る人の癖や動きに寄り添うように変化していきます。
「昨日より今日、少しだけ心地いい」。
そんな微細な変化こそが、永く使っても疲れにくい道具へと育ててくれます。
暮らしの中で働く、小さな相棒として
玄関で靴を履く一瞬、キッチンで煮込みを待つ時間、窓際で本をめくるひととき。
スツールは、暮らしの合間にふっと、生まれる“余白”のような存在です。
場所を選ばず動かせて、座ることも、置くことも、飾ることもできる。
「疲れにくい」という言葉の裏側には、
暮らしのリズムを乱さず、静かに支えるスツールの持つ性格が見えてきます。
スツールに触れてみる
もし、「ちゃんと座れて、ちゃんと立てるスツール」をお探しなら、
出雲のアトリエから生まれた木のスツールを、ひとつの選択肢にどうぞ。
▶ 作品ラインナップ・購入ページはこちら
▶ Instagramで制作風景やスツールのある暮らしを見る
あなたの暮らしの動線に、ひとつ分のやわらかな居場所を。
<大阪万博で参加したプロジェクト「未来の靴のカタチ」の記事はこちらからどうぞ>